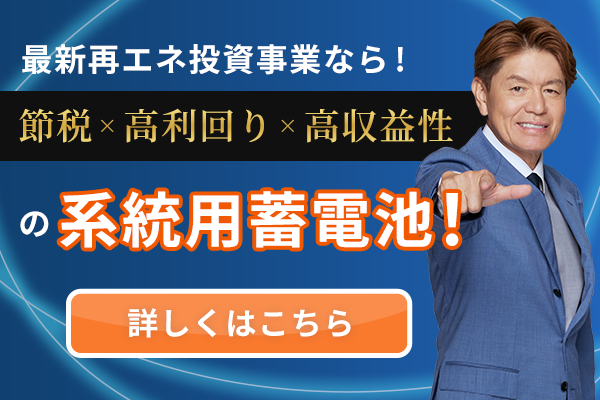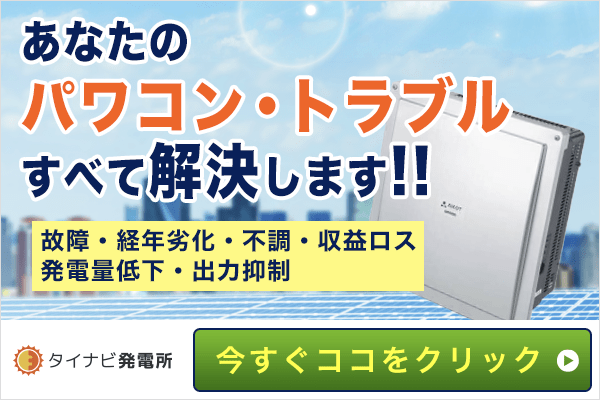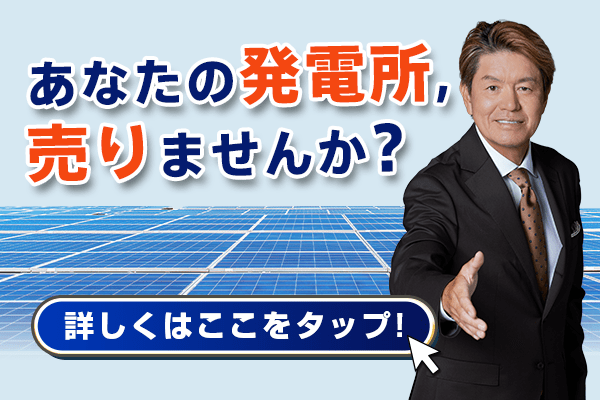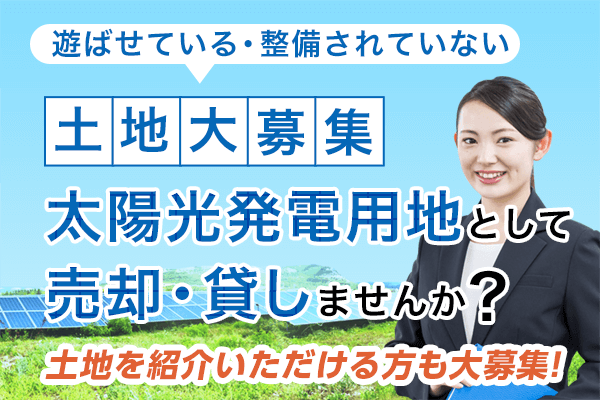再生利用可能エネルギーとして非常に注目されている小型風力発電。国の固定価格買取制度(FIT制度)を利用する売電事業のニーズと相まって、投資熱がかなり高まってきています。
とくに売電価格が高い小型風力発電で気になるのは、年間発電量です。風力発電の発電量は、風の強さはもちろんのこと、風を受ける面積の大きさなどによっても発電量が変わります。小型風力発電はサイズが小さい分、発電できる電力量が少ないのでは?
ここでは、20kWまでの風力発電機器と、50kWの風力発電機器における年間発電量の計算例を挙げて検証していきます。
さらに、年間発電量を向上させる方法や、正確な見積もりを計算する上で注意すべき点などもチェックしていきます。
土地付き太陽光・風力発電の投資物件はタイナビ発電所へ。
特に人気のある物件は会員様限定のご案内です。
※会員限定物件が多数あります。
小型風力発電でも発電容量が20kW未満のタイプの年間発電量

最初に、小型風力発電機器のうち、FIT制度を適用した売電単価が極めて高い20kW以下のものから年間発電量をご紹介します。
ここでは、10kWと20kWの2つのタイプについて、それぞれの具体的な年間発電量を計算していきます。
発電容量が10kWクラスの年間発電量を計算した結果

10kWの発電容量を持つ風力発電機器になると、最低でも1,000万円以上の本体価格のものが主流です。そして、風力発電機器を導入した後に期待できる年間発電量が、どれくらいになるかが大変気になるところ。
まずは、風速9m/秒、発電効率を25%として、月間発電量と年間発電量を計算してみましょう。
月間発電量:10kW✕24時間✕30日✕25%=1800kWh
年間発電量:1800kWh✕12か月=21600kWh
一般的に、小型風力発電で想定されている理想的な風の速さ(定格風速)は、9m/秒になります。日常生活において1秒間に9mの風とは結構強い風ですが、発電機の定格出力を出すにはこれくらいの風速を求められるケースが多いのです。
発電容量が20kWクラスの年間発電量を計算した結果
つぎに、投資効率が最も大きいとされる20kWクラスの風力発電機の年間発電量をチェックしましょう。風の速さは9m/秒、発電効率を25%として計算します。
月間発電量:20kW24時間✕30日✕25%=3600kWh
年間発電量:3600kWh✕12か月=43200kWh
基本的に、9m/秒の風速を維持できる場所となると、居住エリア内で見つけるのはとても困難です。風力発電に理想的な土地を見つけるには、広範な知識と手間をかけなければなりません。
小型風力発電でも容量が20kWを超過するタイプの年間発電量

山の上に立っているような、回転翼の直径が100m弱のタイプは発電容量は数千kWまで大きくなります。導入費用も数億円は下りません。そのため、今回は比較的安い費用で導入できる中小型の50kWタイプを例に年間発電量を計算してみました。
発電容量が50kWのタイプの年間発電量を計算した結果
発電容量50kWの風力発電機に関しても風速9m/秒、発電効率が25%と仮定して計算します。
月間発電量:50kW✕24時間✕30日✕25%=9000kWh
年間発電量:9000kWh✕12か月=108000kWh
20kW以上の風力発電に適用される売電単価は、1kWh当たり約22円(2017年度時点)と大幅に低くなります。基本的にはできるだけ大型のタイプを選び、発電量を多く稼ぐことがポイントになります。
小型風力発電の年間発電量を上げるためのポイントは?

小型の風力発電機器には、それぞれ発電容量が設定されています。しかし、発電容量をフルに使うことなど到底不可能な話です。どんなに小型のタイプであっても、24時間回り続けている機器はまず存在しないでしょう。
風力発電は一般的に冬に発電効率が高くなりますが、他の季節では著しく低下します。年間の稼働率はどんなに良くても30%程度になり、通常は20%から25%が平均的な通知となるのです。ここでは、不安定になりがちな稼働率に左右される年間発電量の向上方法を見ていきます。
発電機器の維持管理・定期メンテナンスを業者に依頼する

小型や大型の風力発電機を問わず、その効率的な運用について大変重要とされるのが機器の維持管理になってきます。そして、この維持管理を定期的に進めることが、年間発電量を向上させることの大きなポイントとなります。
一般的に風力発電機器の回転効率は、使用するたびに悪化することは避けられません。常に外気にさらされ、時には湿気の強い時期もあるので回転部に損傷を来すことは日常茶飯事だからです。
特に発電の稼ぎ時といわれる冬前には確実にメンテナンスを行って、スムーズに使用できるコンディションを回復させなければなりません。大型のタイプが1基で年間1,000万円の維持費が最低でも必要なことを考慮すれば、20kWタイプの維持費は年間で数十万は絶対に下らないのです。
設置場所の選定が最重要になる

風車が正常に動き続けていれば、予測通りの発電量は見込めます。ただし、日本の天気は複雑な地形によって生み出されますので、発電量予測は決して簡単なことではありません。
風力発電の設計上、最もパフォーマンスが良いとされる風速9m/秒を維持できる場所は、山間部くらいにしか存在しないでしょう。そのため、小型風力発電の年間発電量を増やすなら、機器自体の性能以上に設置する場所の選定が重要になってきます。
良い土地を持ってなくても投資できる!風力発電は土地付き(分譲型)物件に注目小型風力発電の年間発電量を正確に計算するための注意点

ここまで、小型風力発電における年間発電量の話を進めてきました。ここからは、より実情に即した正確な数値を計算するために把握しておきたい「実際の風速」について解説します。
年間発電量の計算で意外に考慮されない! 機器の設置高度と風速の関係

小型風力発電を設置するのに適した風速はいくつか、という話は常に出てきます。しかし、実際に風を受ける機器を取り付ける高度までは、多くの方が考慮されていません。
例えば、風速9m/秒レベルの風圧を山の上に設置した20m高さの風力発電機器が得られるとすれば、仮に設置した高さが10m程度になるとその風速は8-8.5m/秒レベルに低下します。しかし、平地になると地上20mの高さでも5m/秒あれば良いほうなので、機器の設置高度が10mくらいだと仮定すれば4-4.5m/秒の風速だと推測できます。
一般的に、高度が10m下がるだけで発電効率が1割ほど落ちることが実証されています。実際の年間発電量の計算には、この設置高度に応じた発電効率を適用することが必要なのです。
つまり、9m/秒で使用想定されている機器でありながらも、その使用高度が著しく低い場合は、風速も半減することが大いに考えられます。そのため、正確な年間発電量を求めるには、設置高度と風速を的確に得てからでないと結果に大きな差が出てきます。
気象庁発表の風速だけでなく、風力階級表も計算に役に立つ

日本で投資されることの多い小型風力発電機器の多くは、10m程度の高さに設置するタイプが多いです。地上10mほどの風力発電となれば、計算に使う風速をどうやって求めればいいか分からないですよね。
ここで役に立つ指標が、気象庁が提供している「風力階級表」です。これは、風の強さを数字で表したものです。風が与える周囲への影響を目で見て確認し、風力階級表を参照すると、地上から10m上の風速が分かるのです。
例えば、等級2になると軽風で木の葉が動くという描写がなされていて、10m上空では1.6-3.3m/秒の風が吹いていることが推測されているのです。また、等級5の疾風では樹木が揺れ始めると説明されていて、8.0-10.7m/秒の風が推定されています。
これがあれば、既定風速の発電容量から換算して現実に合った年間発電量の計算が可能となるのです。
利回り10%を超える風力発電の投資物件も多数!
中でも人気が出そうな物件は、会員様限定公開とさせていただきます。
登録・利用は無料です。ご興味のある方は今すぐ会員登録フォームにお進みください。
※案件が発掘され次第のご紹介になります。
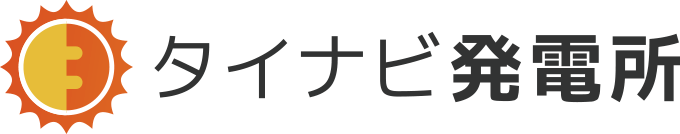
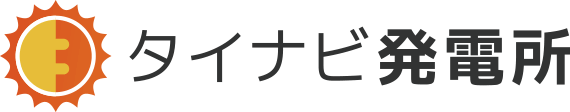




_m.png)






_s.png)

_s.png)