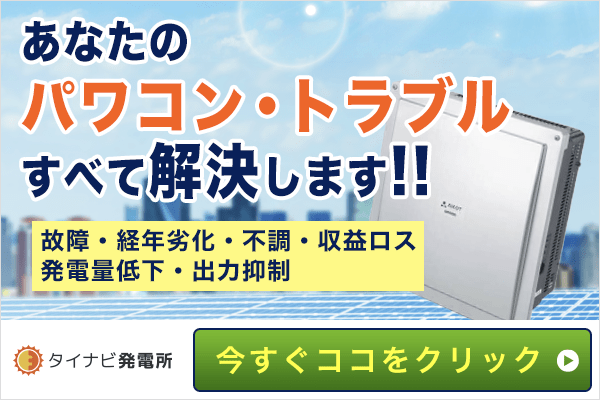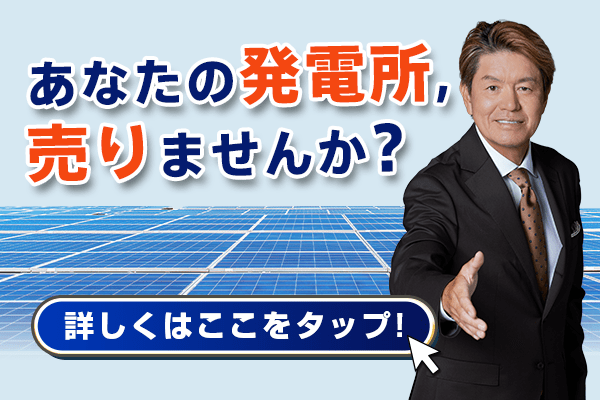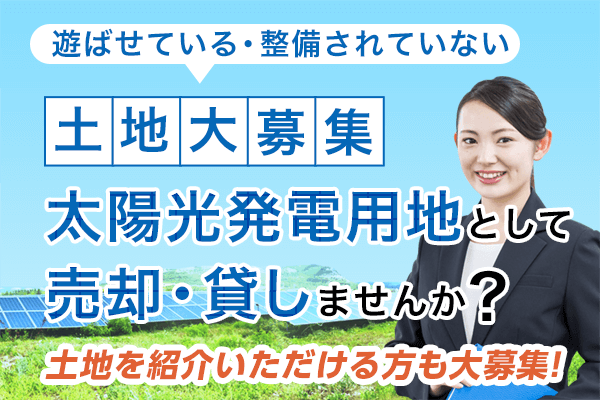太陽光発電投資は、国がクリーンエネルギーを推進していることを背景に拡大してきました。固定価格で電力を買い取る稀有な制度があることから、収入計画が立てやすい資産運用法として需要は尽きません。
一方で、注目度の高さを逆手にとった詐欺も存在しています。実際に被害が出ており、無用な投資リスクを高めるという問題点もあるのです。
安心して太陽光発電投資ができるように、ここでは国民生活センターに相談件数が多い詐欺の手口と、被害に遭わないための注意点などを解説していきます。
土地付き太陽光・風力発電の投資物件はタイナビ発電所へ。
特に人気のある物件は会員様限定のご案内です。
※会員限定物件が多数あります。
なぜ太陽光発電の詐欺が横行するのでしょうか?

そもそも、なぜ太陽光発電関連の詐欺が横行するようになってしまったのでしょうか。その理由を簡単に説明します。
- 購入価格が一般化できない
- 投資商品としてノウハウが広がっていない
- 何度も買う商品ではないので経験を活かしにくい
長い歴史を持つ太陽光発電は、すでに自然エネルギーを利用した発電方法としてはメジャーなものになっています。実際に街中でソーラーパネルを見かける機会も多く、実際に自宅で太陽光発電を始めている人が増えていることを実感できるのではないでしょうか。
その上、太陽光発電には、一定期間決まった価格で電力を買い取ってもらえる「固定価格買取制度」があります。節電だけでなく収益化もできることを知っている消費者も多いでしょう。
しかし、投資商品としての太陽光発電が一般化したのは2012年からのことで、歴史が浅いのも事実です。太陽光市場の成長速度にノウハウ共有が追いつかなかったことで、投資家に十分な防衛力を養えなかった部分があるのです。現状は、詐欺師にとって付け込みやすい情報格差があるといえるでしょう。
資産を守るため、まずは危険な投資話を察知する知識を身につけていきましょう。太陽光発電詐欺の手口をご紹介します。
架空の太陽光発電ファンドに投資させる詐欺の手口

太陽光発電関連の詐欺にはさまざまなパターンがありますが、その中の1つが架空の太陽光発電ファンドへの投資を持ちかけるタイプの詐欺です。
このタイプの詐欺では、架空の太陽光発電所への出資を募り、被害者から出資金を騙し取ります。このパターンは太陽光発電所そのものが存在しないため、出資しても配当金はもらえず、出資金も戻ってきません。
これらの手口から学べることは、太陽光発電所の用地などが実際に用意されている案件だからといって油断は禁物、ということです。出資先が健全な運営母体であるかを見極める必要があるのです。
嘘の説明で契約させる詐欺の手口

太陽光発電詐欺の典型的な例として「事実とは異なる嘘の説明で契約をさせる」という手口があります。
この場合、太陽光発電所も建設予定、あるいはすでに建設済みであり、実際に発電も行われます。しかし、契約の前提となる説明が事実とはまったく異なるため、契約させられた被害者は損害をこうむることになります。
こうした詐欺の流れを紹介しましょう。
まず、実際の発電量からかなり水増しした発電シミュレーションを見せて、確実に儲かるような説明をします。さらに、メンテナンス不要で手間がかからないなど、メリットばかりをアピールして事実とは異なる説明をするのです。
メンテナンスの必要が全くない、というのは嘘

本来、太陽光パネルは、狙った発電効果を出すためには定期的なメンテナンスが不可欠です。これは太陽光発電を導入したことのある消費者には周知の事実です。
機材の定期的なメンテナンス作業を怠れば汚損や故障により発電効率が落ちるだけでなく、最悪の場合は火災や故障を招く事態にもなりえます。
しかし、悪質な業者はそうした説明を一切行わないため、結果として発電機器が使えずに売電ができなくなるなどの損失を被るのです。
相場より高額な工事費を請求する詐欺

実際に太陽光発電システムの設置工事も行い、太陽光発電の売電も開始されるのはよいのですが、相場を超える高額な工事費を請求する業者もあります。
太陽光発電は何度も導入するものではないので、初期費用の相場を知らない人が多いでしょう。悪徳業者はそれを逆手にとって、相場の倍以上もの金額を提示してきます。
工事費が高額になってしまうと、売電収入の利益が減ってしまうことが問題です。悪徳業者が提示する高額な工事費を鵜呑みにしないためには、契約前に相場を理解しておく必要があります。
複数業者の一括見積もりでさまざまな業者の見積もりを見比べれば、太陽光発電システムを設置する工事費用の相場を知ることが可能です。
モニター商法で契約させる詐欺の手口

訪問販売や電話勧誘にはモニター商法を装った詐欺もよくあります。
モニター商法とは、「モニターになってもらう代わりに安く太陽光発電投資ができる」というメリットを提示して、契約を勧誘するものです。太陽光発電が普及する以前は自治体が行っていましたが、太陽光発電が普及した現在、モニター商法を持ちかけてくる場合は詐欺の可能性が高いといえます。
モニター商法を装う詐欺の手口では、モニター価格と称してあたかも割安で購入できるかのように見せるケースが主です。実際は、相場より高い価格が提示されています。
モニター商法詐欺も、太陽光発電システムのコスト相場を知らないという弱みに付け込まれて騙されてしまうため、契約前に相場を知っておくことが大切なのです。
契約後に計画倒産する詐欺の手口

ユーザーが太陽光発電システムの設置費用を支払った後に業者が計画倒産して、行方をくらますというケースがあります。
この場合は、最初からお金を騙し取る悪意を持って契約させたため、明らかに詐欺であるといえるでしょう。しかし、業者に騙す意図があったことを立証することは難しく、支払ったお金を取り戻せないまま、泣き寝入りしてしまう人も少なくありません。
対策としては、このような詐欺が横行していることを頭に入れておき、くれぐれも詐欺の手口に引っかからないように注意する必要があります。
太陽光発電業界はすでにバブルが弾け、生半可な運用をしていた企業はほとんど倒産しています。豊富な実績を持ちながら存続している事業者は、安定性と信頼性が十分にあるといえるでしょう。高額の契約をする前は相手の信頼性をリサーチすることは欠かせません。
発電量詐欺に注意!偽のシミュレーションを見抜くポイント

虚偽の収支シミュレーション結果を提示して「確実に儲かる」とアピールする業者は詐欺の可能性が高いです。ここでは、不正確なシミュレーションを見抜くためにチェックすべき5つのポイントについて説明します。
日照時間ではなく日射量で計算しているか
正確なシミュレーション結果を得るためには、日照時間ではなく日射量で計算しているかどうかを確認することが重要です。
太陽光発電をするときは、収支シミュレーションで発電量と収益を判断します。収支シミュレーションに必要な数値は、「太陽光発電にかかるコスト」「売電価格」「発電量」の3つです。
ここで、「発電量をどうやって知るか」が重要となります。
なぜ日照時間ではだめなのか?

日射量は「光の強さ×面積×時間」で計算します。一方、日照時間は太陽が出ている時間に過ぎず、発電量を左右する光の強さが反映されない数値です。
「システム容量×日照時間」という数式でシミュレーションをして見せる業者がいますが、この計算方法だと、1年中、同じくらい晴れた日が続くことになってしまいます。
実際には発電量が少ない雨の日や曇りの日もあるため、単純に「システム容量×日照時間」でシミュレーション計算をすれば、実際の発電量よりも多い数値が出てしまうのです。
影の損失を考慮しているか
収支シミュレーションをみる際は影による損失が考慮されているかをチェックする必要があります。
発電量を下げる影の影響を反映させずに計算したシミュレーションも、実際の発電量とかなり異なる数値が算出されてしまう場合があるため要注意です。太陽光パネルに影ができれば、当然、発電量は下がり、収益に影響します。
太陽光発電の影になるものは?
影ができる原因となるものは、太陽光発電システムの周りにある木や電柱、フェンスや建物などです。影の量や位置は環境や季節によって変動するため正確な数値を把握しにくいとはいえ、影による損失もシミュレーションに反映されているかどうかをチェックすることによって、業者の信頼度を量ることができます。
パワーコンディショナによる発電ロスを考慮しているか

収支シミュレーションにおいては、パワーコンディショナによる発電ロスも考慮する必要があります。
パワーコンディショナとは電流変換器です。太陽光発電で作られた直流電流をパワーコンディショナで交流電流に変換することによって家庭の電気製品に放電したり、電圧を調整して売電したりといった使い方ができるようになります。
パワーコンディショナで電流を変換する際は発電ロスが生じます。発電効率は太陽光発電システムのメーカーごとに異なりますが、一般的には95〜98%と高水準です。つまり、発電ロスは2~5%程度ですが、発電システムの容量(規模)が大きくなればロスも大きくなります。
そのため、良心的な業者であれば、契約前の発電量シミュレーションにパワーコンディショナによる発電ロス分も計算に入れるのが普通です。
温度上昇による発電量ロスを考慮しているか

収支シミュレーションでは温度上昇による発電量ロスも考慮しなければなりません。
真夏など、日差しが強い日のほうが発電量が増えそうなイメージがあるかもしれませんが、実は、太陽光パネルの温度が下がる冬のほうが発電効率が高いこともあります。なぜなら、太陽光パネルの温度が上がると発電効率が下がり、発電量ロスが発生するからです。
太陽光発電システムの出力基準は太陽光パネルの温度が25度と想定した数値で、温度が1度上がるごとに出力が約0.4%低下するといわれています。
外気温が30〜40度になる真夏において、太陽光パネルの表面温度は60〜80度まで上がります。その場合は14〜22%の発電ロスが発生するため、温度上昇を想定した発電シミュレーションが行われているかどうかもチェックすべきポイントです。
出力抑制を考慮しているか
関東・中部・関西を除くエリアで50kW以上の太陽光発電を検討するときは、出力抑制も考慮する必要があります。
出力抑制(出力制御)とは、電力の需要と供給のバランスを保つ目的によって、電力会社が電気の買取を一時的に停止できる制度です。出力抑制を受けると売電ができなくなり、損失となります。
電力会社によって出力抑制のルールが異なるため、収支シミュレーションをする際は、管轄の電力会社のルールを含めて検討しなければなりません。
詳しくは、下記の記事で説明しています。
実際に詐欺にあってしまった時の対処法

ここでは、実際に太陽光発電投資に関する詐欺被害にあってしまった場合の対処法として、主な2つを紹介します。
クーリングオフをする

クーリングオフとは、特定商取引法に基づき、契約申し込みや契約締結後でも一定の期間内であれば無条件で契約申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。
クーリングオフが可能な期間は契約内容によって定められており、訪問販売の場合は契約日から8日以内であれば契約を解除できます。太陽光発電の訪問販売もこれに該当します。
ただし、設置工事完了後はクーリングオフをするのが難しくなります。そのため、「何かおかしい」と思ったら、契約後でも施工を先延ばしにすることで対処が可能です。
業者がクーリングオフできないといってきた場合や強引に契約させられた場合、あるいは法定書面(申込書や契約書など)に不備がある場合においては、8日を過ぎてもクーリングオフできる場合もあります。
専門家に相談する

悪徳業者から「必ず儲かる」など虚偽の説明をされて契約した場合は、「不実告知」となり契約そのものの取り消しが可能です。法律の専門家に頼ることで、違法な契約の解除がしやすくなります。
クーリングオフできるのかどうか迷う場合や、業者とトラブルになるなど、自分で契約を解除できない場合もあるでしょう。そのような時は自分だけで解決しようと無理をせず、国民生活センターや弁護士など、専門家に相談することで早期に解決できるケースがほとんどです。
詐欺の他にも避けたい太陽光発電に関するトラブル
詐欺ではないとしても、太陽光発電投資には予期せぬトラブルが発生する場合があります。ここでは、太陽光発電投資によくあるトラブル事例を取り上げ、それぞれの対処法を紹介します。
経営悪化による業者の倒産
悪質な計画倒産ではないとしても、資金調達ができなくなって倒産する太陽光発電業者も存在します。太陽光バブル崩壊とされた数年前に高リスクな会社が倒産したため、危うい企業に遭遇する確率は低くなりましたが、念の為に確認するべきポイントです。
融資を受けて太陽光発電に投資する場合は、発電所が完成し、引き渡しが完了してから業者に代金が入金されて、返済がスタートします。引き渡し前であれば費用は発生しないということです。
ただし、引き渡しの前に着手金や中間金などを支払った場合は、引き渡し前に業者が倒産しても、払ったお金は戻ってきません。そうなると、投資はできず、負債だけを抱えることになってしまいます。契約する前に、会社の経営状態をリサーチしておくべきです。
整地不良による破損
屋根ではなく地面に架台を設置して太陽光発電をする場合は、土壌調査と整地の必要があります。しかし、業者によっては、詐欺ではないにしても経験不足や人員不足により、適切な調査や整地が実施されない場合もあるのです。すると、最悪の場合は地盤に亀裂が入り、架台に歪みが生じることもあります。
架台の歪みは太陽光パネルの破損や発電効率の低下を招き、発電ロスになりかねません。土壌調査や整地工事を依頼する場合は、実績のある業者を選ぶことが重要です。
近隣住民とのトラブルで工事中断
太陽光発電所を設置する際、近隣住民の理解が得ておかないとトラブルに発展するケースがあり、最悪の場合は工事を中断するはめになるかもしれません。
トラブルの原因となるのは主に、太陽光パネルの反射光や工事の騒音による問題、森林伐採による土砂災害の心配などです。
反射光問題に対しては、あらかじめシミュレーションすれば回避できます。土砂災害対策としては、芝生などの植物で地表をカバーすることによって水分を吸収し、リスクの低減が可能です。
トラブルを避けるためには、着工前に近隣住民へ対策案を説明し、理解を得られるように努めることが大切といえます。また、中古の太陽光発電所であれば、すでに稼働しているため、近隣住民とトラブルになりにくいでしょう。
太陽光発電投資の詐欺やトラブルに遭わないための対策

こうした太陽光発電投資に関する詐欺に遭わないためには、どのようなことに注意すればよいでしょうか。以下に、具体的なポイントを紹介します。
太陽光発電投資の基本的な情報を身につける
FIT期間や売電価格、平均的な利回り、日射量のデータなど、太陽光発電投資に関する基本的な知識を知っておくことが大切です。もともと、専門的な知識を持たない人でも、インターネットで検索すれば、すぐに情報が得られます。
太陽光発電投資に関する基礎知識を備えておけば、業者が不審なシミュレーションや見積もりを出していないかどうかを見極めることが可能です。
業者の実態や評判を調べる
まずやるべきなのが、本当にその業者が存在しているのかどうかを確認することです。住所が実在するか、法人登記されているかどうかといった点を調べましょう。また、これまでの実績や利用者の口コミなどを調べることも大切です。
自分で発電量のシミュレーションをしてみる

売電シミュレーションの水増しを見抜く方法として、自分で発電量のシミュレーションをしてみるのがおすすめです。
NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が、太陽光発電システムのユーザー向けに日射量のデータベースを公開しているので、シミュレーションをする際の基準にしましょう。
1年間の発電量は、「NEDOで得られた日射量×365日×パネルの容量(kW)×0.8(20%のロス率)」という数式から計算できます。発電量はロス率によって数値が変わりますが、ロス率20%ほどをマイナスした上で計算するのが一般的です。
自分でシミュレーションをした数値と業者が提示したシミュレーションの数値に大きな差がある場合は、太陽光発電投資詐欺を疑う必要が出てきます。
契約させたいがゆえに、エリアの天気が良かった年の実績数値を使用してシミュレーションするなど、意図的に高い発電量を提示している可能性があるためです。
即決を避けて慎重に検討する

たとえ「いい話だな」と思ったとしても即決しないで、検討するという慎重さも重要です。最初から一社に絞らず複数の業者を比較して決める、実際に業者と顔を合わせて話をするなど、自分が納得いくまで検討を重ねることをおすすめします。
また、業者の説明を聞いて少しでも疑問に思ったことがあれば、積極的に質問すべきでしょう。自分でも発電シミュレーションを行い、相手の話の嘘や誇張を見抜けるようにしておくことも大切です。
相手を最初から疑い、質問攻めにすることに対して抵抗感を覚えるかもしれませんが、太陽光発電への投資額は数百万円〜数千万円という高額な金額になります。安心して出資できるよう、自身でも念入りに調査する姿勢が重要です。
太陽光発電投資は納得できる業者を見つけましょう

本記事でも代表的な手口をいくつか紹介しましたが、太陽光発電に関連する詐欺は実際に起きており、被害者も出ています。
太陽光発電への投資は高額な金額が動くことに加え、実際の詐欺の手口を知ると、太陽光発電に投資すること自体に消極的になってしまったのではないでしょうか。
しかし、太陽光発電そのものは将来性もあり、魅力的な投資先であることも事実です。消費者を騙そうとする悪徳業者はごく一部の存在であり、投資に対して第三者的な立ち位置から優良業者を紹介するサービスもあります。一部の悪評を聞いて「太陽光発電はダメ」と決めつけてしまうのは、結論を急ぎすぎているといえるでしょう。
太陽光発電は長期間安定した収益を上げることが期待できるため、投資初心者でも投資しやすいというメリットもあります。詐欺のリスクは確かに注意すべきものですが、予備知識を持ち、事前に準備・確認した上で、信頼できる業者と契約すれば詐欺被害に遭わずに投資を行うことができます。
最終的には、投資家本人の責任が問われることでもあります。自分でも納得のいくまで調べて信用できる投資先を探すことが大切です。
土地付き太陽光・風力発電の投資物件はタイナビ発電所へ。
特に人気のある物件は会員様限定のご案内です。
※会員限定物件が多数あります。
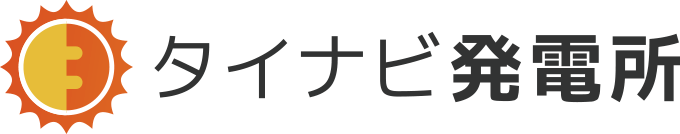
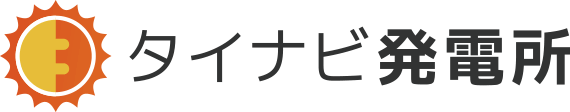












_s.png)