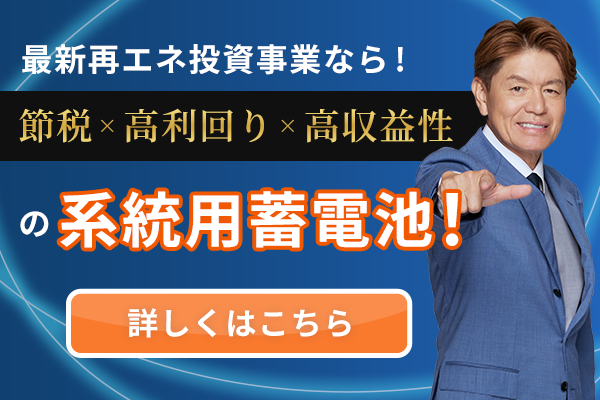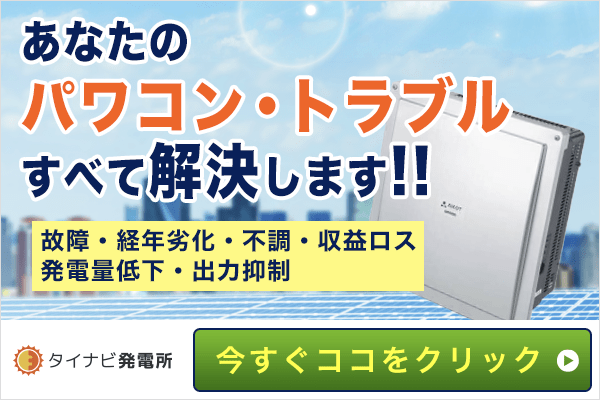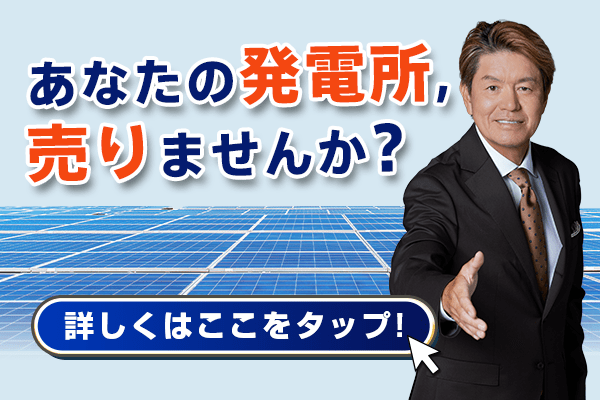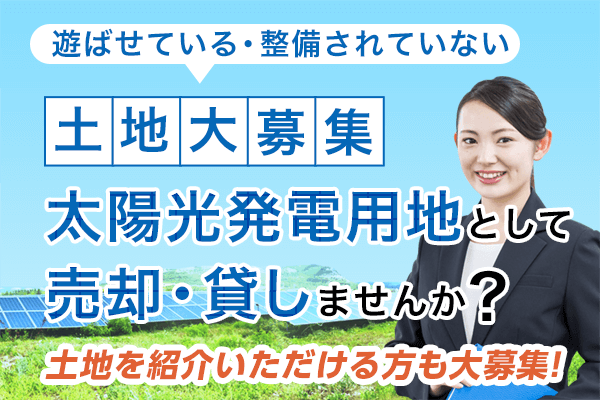本気で投資を検討するなら、将来の展望や、売却などの終わるときの出口を含めて考えますよね。
太陽光発電投資は登場から20年も経っておらず、売電投資を最後までやりきった方はいません。
そんな環境で実際に投資を行うとなると、今後の展望に不安を抱く投資家も多いのではないでしょうか。
ここでは太陽光発電への投資を考えている人を対象に、太陽光発電のこれまでの流れと今後の展望、そして現時点で有効な出口戦略について解説します。
土地付き太陽光・風力発電の投資物件はタイナビ発電所へ。
特に人気のある物件は会員様限定のご案内です。
※会員限定物件が多数あります。
日本の太陽光発電普及の流れ

太陽光発電につながるような発見をしたのは、アメリカの研究者でした。1954年のことです。その後は、アメリカの人工衛星における太陽光発電の実用化に始まり、日本でも1960年代前後から太陽光発電の研究や開発が行われるようになりました。
では現在の日本で、太陽光発電を取り巻く状況はどのようになっているのでしょうか。以下では、普及に至るこれまでの流れについて解説します。
2009~2023年までの価格の推移
太陽光発電の売電が初めて制度化されたのは2009年のことです。それ以降の産業用太陽光発電の売電価格は年ごとに価格が改定され、前年よりも値下がりしていく傾向が見られます。
注意!認定を受けたFIT価格は20年間キープされます
FIT価格が毎年下落するというニュースが流れますが、すでに認定を取得した発電所の買取価格は下落しません。FIT認定を受けて、買取価格が決まれば、その価格を20年間キープできるのがFIT(固定価格買取制度)です。
FIT制度は固定価格が20年間続きます。発電所ごとにFIT価格が決まり、その固定FIT価格で20年間売電する事ができますので、ご安心ください。
太陽光発電のFIT買取価格の推移
| 2012年 | 40円/kWh(税別) |
|---|---|
| 2013年 | 36円/kWh(税別) |
| 2014年 | 32円/kWh(税別) |
| 2015年 | 29円/kWh(税別) 27円/kWh(税別)※ 7月以降 |
| 2016年 | 24円/kWh(税別) |
| 2017年 | 21円/kWh(税別) |
| 2018年 | 18円/kWh(税別) |
| 2019年 | 14円/kWh(税別) |
| 2020年 | 12円/kWh(税別) ※ 3割自家消費で+1円 |
| 2021年 | 11円/kWh(税別) ※ 3割自家消費で+1円 |
| 2022年 | 10円/kWh(税別) ※ 3割自家消費で+1円 |
2023年 | 9.5円/kWh(税別) ※ 3割自家消費で+1円 |
2023年現在は、産業用太陽光発電のFIT固定買取単価は9.5円/kWh×20年間です。
ソーラーシェアリングや自家消費要件を満たす太陽光発電所は11円/kWh×20年間となります。
これからFIT認定を取る太陽光発電所は、全量売電するか3割自家消費するかでFIT価格が変わります。あなたの投資計画に適したFIT価格をよくご確認ください。
2023年までの太陽光発電市場の主なニュース
2009年に売電が始まって以降、2012年の固定価格買取開始などをはさみ、太陽光発電をめぐる状況には様々なニュースがありました。
以下では、2009年から2021年までの太陽光発電における主なニュースを紹介します。
電力会社の売電保留問題はすでに解消

太陽光発電で売電するためには、電力会社の送電網にあなたの太陽光発電所を接続してもらう必要があります。ところが、電力会社による連系対応が数カ月も保留されたため、新規の太陽光発電が売電を始められずに問題となった時期がありました。
現在ではこの問題は全国的に解消されています。
きっかけとなった九州電力による買取中断・接続保留問題は、「九電ショック」と言われています。詳しくは次のような内容です。
2014年9月、九州電力が再生可能エネルギーの買取中断を検討するとの一報が流れました。これを受けて他の電力会社も追随する動きを見せたため、太陽光発電の売電を取り巻く状況に大きな変化が生じることとなりました。結果的にこの時には、東京電力、中部電力、北陸電力以外は買取中断を決定しました。
この件では系統制約の課題が浮き彫りになりましたが、これを解決するための様々な改革が行われている最中です。
FIT法改正が投資にもたらした変化

2017年4月、いくつかの点が改正された改正FITが施行されました。改正FITがこれまでと何が異なるのかというと、発電事業者側に影響があるポイントは大きく3点です。
1つ目は、申請方法の複雑化です。従来は、発電設備を確認するだけの「設備認定」でした。しかし改正後は、事業計画をしっかりと確認する「事業認定」となっています。
2つ目は、イニシャルコストの増加です。発電設備の周囲にフェンスの設置が義務化され、また、設備規模によっては事業者名等を記した標識の設置も義務付けられています。
3つ目は、ランニングコストの増加です。改正FITによって、設備の保守点検や維持管理が義務付けられました。
これら3つのポイントは、いずれも発電事業者に対し、責任をもって安定的な発電を行うことを促すような改善内容となっています。事業者側も、よりしっかりとした意識を持つことが必要です。
廃棄費用の積み立てルールが決定
2018年7月に太陽光パネル等の発電所の廃棄費用の積み立てが義務化されました。
国としては太陽光発電の売電期間(20年間)が終了したあと、役目を終えたシステムが山林などに放置されることを危惧しています。将来的に発電システムを撤去する費用を発電事業者に積み立ててもらう制度になりました。
積立スタートは2022年4月からです。
「FIP」は2022年度から段階的に範囲が拡大
FITと似ているようで大きく異なるFIP制度が始まりました。FITがいつでもずっと同じ価格で電気を買い取るのに対し、FIPは電気の需要と連動して刻々と売電価格が変動します。
売電収入が市場価格に振り回されるように思われますが、一定のプレミアム交付によって基本的にはFITと同程度の収入になる想定の制度です。
さらに、電気の需要が高い時間やシーズンにたくさん売電できる仕組みを持つと、FITにはないほどの増収機会を得ることができます。
収支計算とシミュレーションが難しいので、太陽光発電の販売業者とよく確認しておくことをおすすめします。
FIPの対象設備
FIPの対象となる設備は年度ごとに拡大していきます。ただし、50kW以上の太陽光発電所は任意でFIPを選択することもできます。
| 年度 | FIP(入札)限定 | FIP(入札対象外)も選べる |
|---|---|---|
| 2022年度 | 1000kW以上 | 50kW以上 |
| 2023年度 | 500kW以上 | 50kW以上 |
| 2024年度 | 250kW以上 | 50kW以上 |
インボイス制度
消費税を巡るインボイス制度は太陽光発電にも影響があります。
ただし、
インボイス登録の有無によってFIT買取価格が変わることはありません。
いままで消費税を納めてこなかった事業者や個人投資家が売電収入のためにインボイス登録する必要はありません。しかし、収入によっては全量売電の売電収入にかかる消費税について、インボイス制度の影響を受ける人が出てきます。
ケースごとにとるべき対応が異なりますので、ご自身の状況を確認してください。
住宅用太陽光発電システムの余剰売電
売電以外も含めた課税収入が1000万円を超えない人
免税事業者
売電以外も含めた課税収入が1000万円を超える人
課税事業者※ この先、課税事業者はインボイス登録をしないとFIT認定が受けられなくなる予定です
屋根型区分の新設
2023年下半期から、10kW以上の事業用太陽光に「屋根型」という区分が新設されます。一定以上の発電規模なら、地面に建てるよりもコストが安く、売電価格を高くして全量売電できます。
その特徴は、
- 売電価格が高い
- 50kW未満は自家消費型の地域活用要件の対象
- 集合住宅は自家消費要件の達成が比較的簡単に
既築建物の屋根に設置する太陽光の場合は、250kW 以上でもFIT・FIP 入札を免除されます。
集合住宅の屋根に設置する太陽光発電(10-20kW)については、自家消費型の地域活用要件の対象ですが、達成の条件が緩和されます。
配線図などから自家消費を行う構造だと確認できれば、30%以上の自家消費を実施しているとみなされ、屋根型区分の認定が受けられます。
FIT終了後の太陽光発電の展望

FITが終了してしまうと売電価格はどうなるのか。
また、太陽光発電自体を取り巻く環境はどのようになっていくのか、今後の動きが心配な人もいるかもしれません。
ここからは太陽光発電のFIT終了後の展望について解説します。
FIT終了後の売電価格を予測

産業用太陽光発電は2012年にFIT売電をスタートしたため、20年間のFITが終わった後の売電価格はまだ明らかになっていません。
FIT外での売電価格の参考になるのは、一足先に卒FITを迎えた設備が多数出ている住宅用の太陽光発電です。
住宅用太陽光発電のFITは10年間ですから、制度が始まった当初の2009年頃に始めた世帯はすでにFITが終了しています。FITが終わった後、住宅用太陽光発電に起こった変化は次のとおりでした。
- 買い取り価格はFITに比べると大幅に下がりました
- 今までの電力会社へ売電を継続できます
- 売電先の電力会社を乗り換えできるようになりました
売電の継続と契約先の変更は、産業用太陽光発電でも実現されるでしょう。気になるのは、売電価格ですよね。
あくまでも参考ではありますが、経済産業省の資料によると10年目以降の売電価格は11円/kWh前後になると想定されています。
これまでの売電価格と比較すると大幅に下がることになります。このタイミングまでに元を取り、設備更新と売却することも視野に入れて運用計画をたててください。
FIPで売電価格が高まるケースも?
2022年から始まる市場連動型の買取制度FIPの価格に注目です。これは市場で取引されている電気料金単価と連動し、買取価格が決まるシステムです。
近年はJEPX(電力卸売市場)での電気の取引価格がかなり高騰していることから、卒FITの買取単価よりも高値が付く可能性もあります。
住宅用「2019年問題」から見る太陽光発電の今後

「2019年問題」をご存知でしょうか。これは、住宅用の余剰電力について、2009年から始まった固定価格買取期間が終了する年をとって名付けられた問題です。2009年当初から住宅用太陽光発電で売電を始めた設備は、2019年以降の売電価格は未定となるため、不安視している人もいました。
結果として、2019年には固定買取期間が終了した家庭に対して数々の電力会社が8円/kWh~12円/kWhというレンジの買取プランを発表しました。いまでは大手・新電力を含む40社以上の電力会社が買取プランを提供しています。
売電価格の下落対策は自家消費?遠隔地はどうする?
FITが終わると売電価格が大幅に下がるため、売電するよりも自家消費する人が増えたのも事実です。太陽光発電の電気を無駄なく使うために、多くの人が蓄電池を購入しました。
このように、住宅用太陽光発電は売電しなくても自宅で消費することは可能です。しかし、郊外に設置している産業用太陽光発電では、自家消費するという選択肢は考えにくいでしょう。そもそも、全量を売電する前提で連系工事している設備を、余剰売電に切り替えられるかという問題もあります。
そこで野立て太陽光発電所の所有者が注目するべきは、2021年からスタートしたオフサイトPPAという新しいビジネスの事業者です。
オフサイトPPAとは?

投資用として普及している野建てのFIT案件が卒FITを迎える頃、オフサイトPPAモデルを活用する事業者が発電所を大量買取りに回る可能性があります。
PPAとは、太陽光発電を初期費用0円で設置できるモデルです。
PPA事業者は契約者の屋根に太陽光発電を設置して、初期費用やランニング費用を負担します。
その太陽光発電から発電される電気は契約者に一定期間、電気を販売し続けます。
契約期間を満了すると、太陽光発電設備は契約者のものになります。
PPAには、オフサイトモデルとオンサイトモデルがあります。野立てで設置された投資用発電所はオフサイトモデル、屋根に付けて自家消費もする発電所はオンサイトモデルと区別されます。
オフサイトモデルは野建てなどに太陽光発電を設置して、そこから発電する電気を電力会社が系統を介して第3者の需要家に販売します。
これはFITを終えた投資用太陽光発電を活用できるビジネスですので、電気の仕入れに使える太陽光発電所を買い取って回ることが予想できます。太陽光発電投資の基本的な出口戦略は売却という流れは変わらないでしょう。
FIT終了後の投資家の選択肢1.発電所の売買

FIT終了後に売電や自家消費が上手く行かなかった場合、投資家の選択肢の1つとして挙げられるのが、発電所の売買です。
そもそも、日本のエネルギー自給率が低いという問題点は、FITが終了しても変わりません。エネルギーの選択肢を増やすために、政府は太陽光発電の継続を推進しています。太陽光発電への需要が急になくなるということは可能性として低く、発電所の売買も十分に成り立つと思われます。
太陽電池のセカンダリー市場拡大

太陽光発電の発電所ごと売却するという方法が成り立ち得るのには、太陽光発電のセカンダリー市場が拡大を見込まれているという理由もあります。
既に中古の太陽電池モジュールに関しては、投資家や新電力事業者による購入が増加しています。その流れで、発電所についても売却を考える所有者が増える可能性があるのです。
発電所ごと売却することにはメリットがあります。それは、過去の発電実績や施工品質、メンテナンス実績を見せることができるため、その分を売却価格に強く反映させられるという点です。
加えて、設備を土地ごと売却するため、モジュールだけを売るよりも売却価格は高くなる可能性が大きいです。発電量の実績データがあれば、売値交渉の好材料になるでしょう。
もし、売却を考えている方はタイナビ発電所の売却専任スタッフが様々な相談~査定~売却までワンストップ売却サービスを提供しております。相場を知らずに、買い叩かれるケースも増えておりますので、是非ご相談ください。
土地付き太陽光発電所の売却査定はタイナビ発電所へ。
太陽光業界の売買実績4000件以上の経験と豊富な販路で売却買取・売却仲介・発電事業売却などトータルでサポートいたします。
※税理士相談無料!売却依頼後に24時間以内に簡易査定させていただきます。
FIT終了後の投資家の選択肢2.発電所の廃棄

思い切って発電所を廃棄するということも、FIT終了後の選択肢として考えておくべきです。廃棄というのは、太陽光発電を自費で撤去し、賃借した土地なら返却できるよう原状復帰するということです。
ただし、この廃棄費用は利回りを圧迫しません。なぜなら、FITの買取価格は、廃棄時の撤去費用も考慮して決定されているのです。
FIT制度を適用するために作成する事業計画でも、廃棄費用やその積立額を記載することが求められています。さらに、10kW未満の太陽光発電を除く全てのFIT設備に廃棄費用の報告が義務化されました。
関連リンク:『廃棄費用(撤去及び処分費用)に関する報告義務化について(周知)』経済産業省 資源エネルギー庁
売電で得た収入を全て使ってしまうのではなく、廃棄の時の積立額には手をつけないための資金計画が重要です。
太陽電池モジュールのリサイクル事例

太陽電池モジュールのリサイクルも、太陽光発電の普及が進むにつれて注目されるようになっています。
現在の日本では、太陽電池モジュールは一部分を除いては破砕されて処理されることが多いです。
今後、モジュールに使われているガラスや金属などを破砕せずに分離回収する技術が確立すれば、太陽電池モジュールに使われている素材を全てきれいに再資源化することもできるようになります。
新たな市場を生み出し、ビジネスチャンスとなる可能性があります。
再エネ発電は今後も拡大方針の流れ 波に乗るのは遅くない

太陽光発電の売電価格は年々下がっているとはいえ、政府が「エネルギーミックス」で再生可能エネルギーの拡大方針を明確にしており、太陽光発電の接続量を増やせるような電力改革も並行作業で行われています。
再生可能エネルギー発電が今後も拡大の流れになるであろうことは、ほぼ間違いがありません。加えて、FITによって利回りが平均10%となっている太陽光発電への投資は、他の投資よりもローリスクで利回りも高いです。
今であれば政策の流れにも乗っているため、ローンを組んで始めることもできます。発電所の売却など、設備の処分方法やFIT終了後の対策法がないわけではありません。
新たな投資先を考えている人は、この機会に太陽光発電への投資を考えてみてはいかがでしょうか。
土地付き太陽光・風力発電の投資物件はタイナビ発電所へ。
特に人気のある物件は会員様限定のご案内です。
※会員限定物件が多数あります。
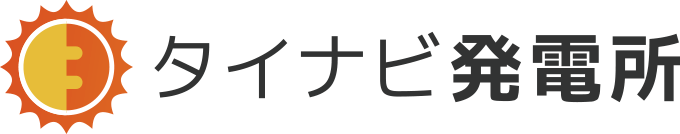
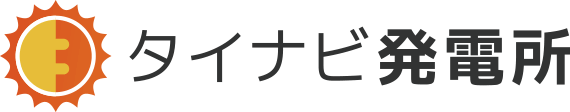











_s.png)