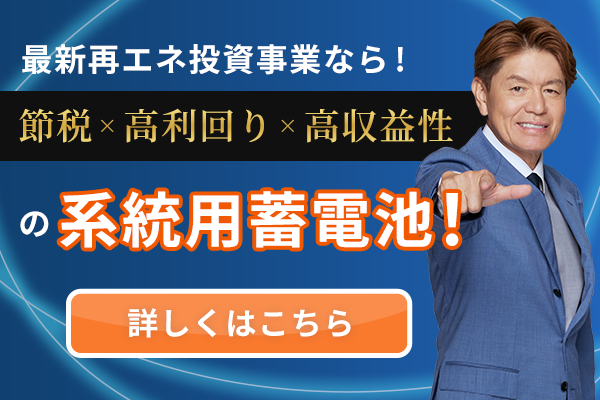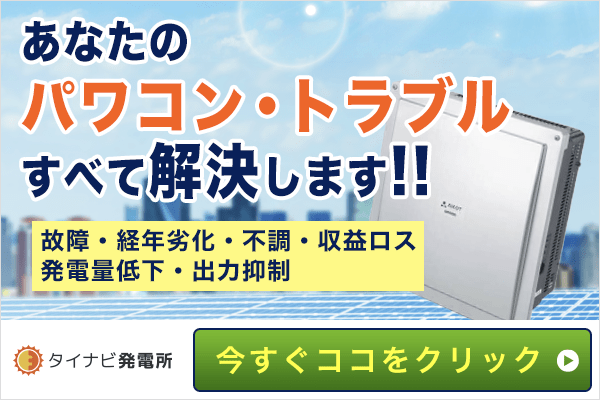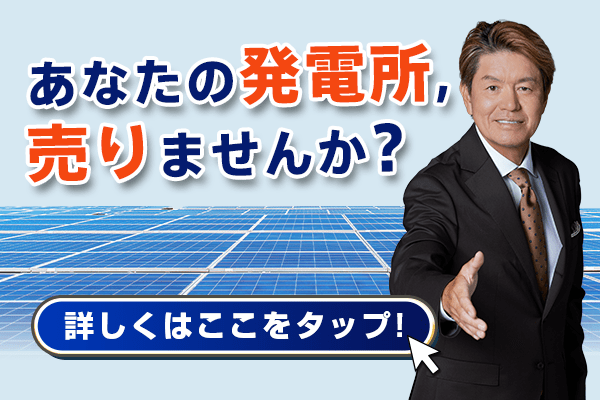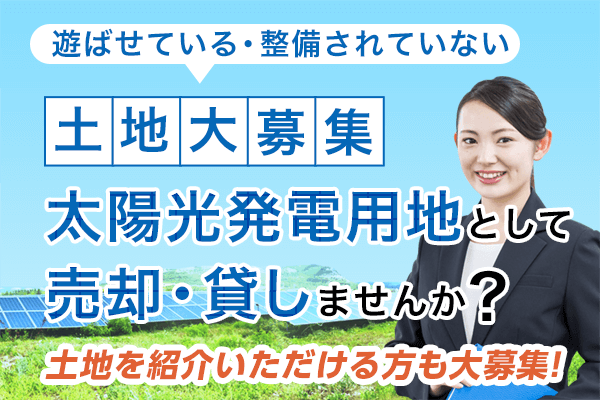エネルギー・インフラ業界は、世界的に脱炭素社会の実現が求められる中、特に石油・ガス・電力分野では、これまでにない規模での構造転換が進行しています。再生可能エネルギーの拡大、水素やアンモニアといった次世代エネルギーの導入、老朽インフラの再整備など、業界全体が変革期に突入しています。
この流れの中で、M&A(企業の合併・買収)は、事業の多角化、技術力の獲得、スケールの拡大などを目的に活発化しており、特に中堅・中小企業にとっては生き残りをかけた重要な選択肢となっています。
このように、エネルギー・インフラ業界では、石油・ガス・電力といった既存分野に加え、自由化による競争激化と脱炭素の流れを背景に、再エネなどの新たな代替エネルギーが大きな潮流となっています。
当然、このような変化の波により、石油・ガス・電力業界におけるM&Aも増加しており、M&Aの流れは、今後も継続的に加速していくことが予想されます。
では、エネルギー・インフラ関連企業(石油・ガス・電力)にとっては、競争力維持だけでなく、どのような競争戦略が求められるのでしょうか?
本記事は、再生可能エネルギー業界で14年間にわたりタイナビシリーズ等のWebプラットフォームをを展開する株式会社グッドフェローズのM&A専門家が最新のM&A動向を解説し、具体的に会社売却・買収を考えている経営者の皆様へ、エネルギー業界に特化したM&A仲介サービス「タイナビM&A」についても解説しますので、最後までぜひお読みください。
エネルギー・インフラ業界の過去・現状・今後の展望

20年前は競合参入もなくとても安定していたエネルギーインフラ業界ですが、この14年は安定から競争環境に代わり、そしてその存在も淘汰される可能性がある厳しい14年間となりました。また、今後も代替エネルギーの更なる参入により、さらに厳しい市場となることが見込まれています。
1:安定供給重視の時代(~2010年)
日本のエネルギー供給は、長らく大手電力・ガス・石油企業による寡占構造のもと、「安定供給」を最重要視してきました。都市ガスとLPガスの二大市場では、インフラ整備が進んだ都市部では都市ガス、地方ではLPガスが主流となり、それぞれ独自の市場が形成されていました。
2:電力・ガス自由化!シェール革命・再エネの波(2010年~2019年)
米国のシェール革命によって化石燃料の国際価格が変動、日本のエネルギー調達にも影響を与えました。一方、国内では2012年の固定価格買取制度(FIT)導入を契機に再生可能エネルギーの導入が進展。電力の全面自由化(2016年4月~)、ガス自由化(2017年4月~)も実施され、競争が激化しました。LPガス業界では自由化の影響とともに、オール電化や人口減少による需要減少、後継者不足などの課題が浮き彫りとなり、業界再編の必要性が高まりました。
3:脱炭素・GX(グリーントランスフォーメーション)時代(2020年~2023年)
政府の「2050年カーボンニュートラル宣言」を受け、エネルギー・インフラ企業はGX(グリーントランスフォーメーション)に向けた取り組みを本格化させました。再エネ投資の拡大、EVや蓄電池などの関連分野への参入も進む中、2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、燃料価格の高騰を招き、新電力各社の経営を直撃。逆ざや状態に陥り、撤退や倒産が相次ぎました。
ガス業界でも、特にLPガス事業者は需要減と後継者不在により、M&Aを通じた事業承継・再編が進行。GXに伴うバイオガスや合成メタン導入の動きも注目され始めています。
4:水素・アンモニア・CCUSの実装時代へ(2024年~2025年)
GXの柱として位置付けられる水素・アンモニア、そしてCCUS(二酸化炭素の回収・利用・貯留)といった次世代技術の社会実装が本格化する見込みです。インフラ整備や地域連携を視野に入れた、企業間連携・統合が加速していくと見られています。
このように、エネルギーインフラ業界の環境は大きな制度変更及び再エネ・水素等の代替エネルギーの到来により大きく変化しています。
エネルギー・インフラ業界のM&Aで押さえておくべきポイント
.png)
今後、電気・ガス・石油などのエネルギー業界で出口・M&A戦略を考えている企業経営者は、次のポイントを押さえておく必要があるでしょう。
非化石電源の確保(再エネ・蓄電池設備の取得)
再エネ電源(太陽光・風力・バイオマスなど)の確保は、GX実現に向けた基盤となります。また、再エネ由来の発電は天候等により変動が大きいため、蓄電池を併設することで、安定供給と市場価値の最大化を図る動きが進んでいます。非化石価値取引市場への対応も、今後の戦略要素です。
卸電力市場依存からの脱却(自社発電・調達力の強化)
近年のJEPX(日本卸電力取引所)の価格高騰を背景に、電力小売事業者は市場価格リスクを強く意識するようになっています。そのため、自社で発電設備を保有する、または長期PPAを締結するなどの手段で安定した電源確保の重要性がますます高まっています。
ガス事業の広域連携・事業承継
LPガス・都市ガス業界では、人口減少やオール電化の影響により需要が減少傾向にあります。さらに高齢化による後継者不在問題も深刻であり、複数地域をカバーする広域企業への統合が加速しています。M&Aによって、スケールメリットの追求や業務効率化を図る動きが主流です。
水素・アンモニア技術保有企業の買収
水素やアンモニアは、火力発電所の燃料転換や産業用途での利用が期待される次世代エネルギーです。製造・輸送・貯蔵に関する技術を有するスタートアップや研究機関と連携・買収することで、企業はGX市場における競争優位性を確立できます。
GX・高度化法への対応(非化石比率44%以上)
エネルギー供給構造高度化法(高度化法)」では、2030年に向けて非化石電源比率を44%以上とする義務があります。これにより、再エネ・非化石証書の取得や、高効率設備・クリーン燃料への切り替えが急務となっており、M&Aによって対応力の高い企業を取り込む戦略が重要視されています。
今後エネルギー・インフラM&A市場に影響を与える制度について

今後予定されている制度変更で、市場に影響を与える内容について記載します。
制度内容の詳細によっては大きく変化する可能性があります。
GX投資促進法
正式名称は「脱炭素成長型経済構造移行推進法」となり、GX(グリーントランスフォーメーション)を実現するため、企業の脱炭素設備への投資に対して税制・財政の両面から支援を行う制度です。
再生可能エネルギー設備、蓄電池、水素・アンモニア供給設備、カーボンリサイクル設備などが対象となり、最大10%の税額控除や特別償却といったメリットがあります。認定されたGX事業計画を基に補助が行われ、M&Aで取得した企業の設備拡張にも適用可能です。
GXリーグ
経済産業省が主導する、脱炭素社会の実現に向けた企業間連携の枠組みとなり、GXリーグに参加する企業は、自主的なCO2削減目標を設定し、カーボンクレジットの取引や再エネ導入などを通じて脱炭素経営を推進します。
参加企業は、今後の制度設計や排出取引市場にも影響力を持つ可能性があり、ESG投資やM&A時の評価にも好影響を及ぼすと考えられています。
カーボンプライシング(排出量取引・炭素税)
CO2排出に「価格」を設定し、排出削減を促す仕組みであり、日本においてはGX-ETS(GX排出量取引制度)が試行段階にあり、将来的には対象企業の拡大と市場本格運用が進む見込みです。
これにより、排出量の多い企業は実質的なコスト負担を強いられるため、排出量の少ない企業とのM&Aや再エネ企業の買収が進むと見られます。
水素・アンモニア供給支援スキーム
水素・アンモニアの普及を目的に、供給インフラの整備、輸送・貯蔵・製造にかかるコスト補填を国が支援する制度であり、導入初期は価格競争力が弱いため、一定期間価格補填を行い、民間事業者の参入を後押しします。
水素・アンモニア関連技術や拠点を持つ企業の価値が高まり、今後のバリューチェーン構築を見据えたM&Aが活発化する見通しです。
高度化法による非化石電源の導入義務
エネルギー供給構造高度化法に基づき、電力・ガス小売事業者は2030年までに非化石電源比率を44%以上にする義務があり、電力会社は再エネ電源や非化石証書の取得が必要不可欠であり、非化石資源を保有する企業や、蓄電池を備えた発電所などがM&A市場で高い評価を得るようになります。
ただ、現実に電力会社の中で再エネ電源を自社で大量保有しているケースは少ないことから、大量に発電所アセットを保有する事業者の買収・資本提携が増える事が予想されます。PPAスキームを活用して再エネ供給量を増やすのは長期的には友好的ですが、短期的に増やす方法は資本提携・M&Aが勝ち筋です。
これらの制度は、再エネや脱炭素関連企業の価値を大きく押し上げる一方で、従来型の化石燃料中心の企業にとっては大きな転換点です。制度対応が経営戦略の一部となる中で、M&AはGX対応を加速させる有効な手段として注目されています。
近年のエネルギー・インフラ業界M&Aの概要
近年のエネルギー・インフラ業界でのM&A事例です。
以下は既にプレスリリース等で公表されている情報となります。
- □東京ガスとレノバとの資本業務提携
- □ENEOSホールディングスが(JRE)ジャパン・リニューアブル・エナジーの全株式取得
- □大東建託、バイオマス発電会社を買収
- □日本瓦斯(ニチガス)は同業のLPガス会社を買収
- □looopと東急不動産の資本業務提携
このようなM&A事例より、今後どういったM&Aが注目されるだろうか?
2025年度以降に予想されるM&A動向
2025年以降、エネルギーインフラ市場ではさらなるM&Aの加速が予想されていますが、そのM&Aパターンを大胆に予測します。
1. 高度化法対応に向けた非化石電源の取得競争
非化石比率44%以上を義務付ける高度化法により、電力会社やエネルギー企業が再エネや蓄電設備を確保するための競争が激化する見通しです。
実際に、2025年4月に契約件数約34万件以上の電力事業を展開するLooopと日本全国に約2GW程度の再エネ設備を保有する東急不動産の資本業務提携は、この流れを象徴しています。
2. LPガス事業者の事業承継M&A加速
少子高齢化と後継者不在の影響により、LPガス事業者は存続のためにM&Aを活用した事業承継を選択する動きが強まっています。
3. 水素・バイオガス・合成メタン関連企業の統合
GX推進におけるキーテクノロジーであるこれらの分野では、研究・開発から供給までを一体化させたビジネスモデル確立のために企業統合が進むと予想されます。
4. 地域電力・ガス企業による広域ネットワーク化
地域限定で展開していたエネルギー事業者がスケールメリットを追求し、広域でのネットワーク構築を進めるために統合・提携を進めています。
5. IT・AI企業によるエネルギーテック領域への参入M&A
需要予測や需給調整、電力取引などの分野でIT・AI技術の活用が進み、異業種からのM&Aによるエネルギー市場参入が増加しています。
では、実際にエネルギーインフラ業界で会社売却・事業継承・M&A戦略を検討中の企業はどうすれば良いのでしょうか?
業界に特化したM&A会社に依頼するメリット

今後M&A(買収)を検討している企業や、出口を模索する再エネ関連事業者はどこにM&Aを依頼すべきでしょうか?
M&A業界に多数の仲介サービスを提供している企業がありますが、数が多くてどこに依頼すべきか迷うでしょう。
そこでオススメなのが、業界が狭いほど業界に特化しているM&A会社をお勧めします。
業界に特化したM&A企業に頼むメリット
- ● 専門的な知識・経験
業界特有の規制、事業などに精通しているため、適切なアドバイスが可能。 - ● ネットワークの活用
業界内の買手・売手ネットワークを持っており、マッチング精度が高い。 - ● 案件価値の正確な評価
業界特有の収益モデルやリスクや市場性を考慮し、正確なバリュエーション価値が算出可能。 - ● 交渉力の強さ
業界内での豊富な実績により、買手・売手双方にとって有利な条件での交渉が可能。 - ● 契約・法務対応のサポート
業界特有の法規制に精通し、スムーズな契約締結をサポート。
★ 業界特化のM&A会社に依頼することで、業界に合わせた会社価値の算出だけでなく、M&Aの売買スピードも期待できます
このように、専門性の高いM&A会社に依頼することで、スムーズかつ高精度な取引が実現しやすくなります。
エネルギー業界でM&A(買収・売却)を検討中の方へ – タイナビM&Aの活用

エネルギー業界(再エネ・電力)に特化したM&Aを検討している方におすすめなのが、株式会社グッドフェローズが運営する「タイナビM&A」です。
グッドフェローズは、再エネ業界でタイナビシリーズ等のWebプラットフォームを展開しており、太陽光・蓄電池・PPA・新電力・NONFIT・蓄電所・風力・バイオマスなどの関連企業を事業通じて全国的な大規模なネットワークを構築、日本全国の太陽光発電事業者の約20%を会員データベース化しております。
- ● 豊富な業界ネットワーク:1,000社以上(メーカー、商社、大手EPC、電力会社)のエネルギー関連企業
- ● 経験豊富なチーム体制:10年以上の実績を持つプロフェッショナルが対応。
- ● 着手金・相談料無料:成功報酬型でリスクなし。
- ● 高いマッチング率:エネルギー事業に精通しており、企業価値を適切に算定。成約率は33%。
「タイナビM&A」は、エネルギー関連案件に関する専門的な知識を持ったプロフェッショナルが対応し、事業ポートフォリオの最適化や収益の最大化を支援します。
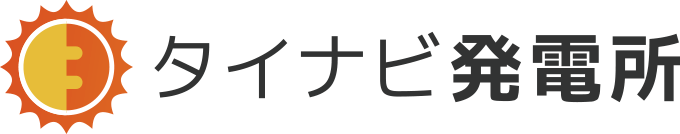
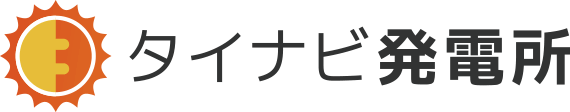




_m.png)

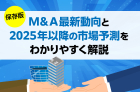




_s.png)

_s.png)