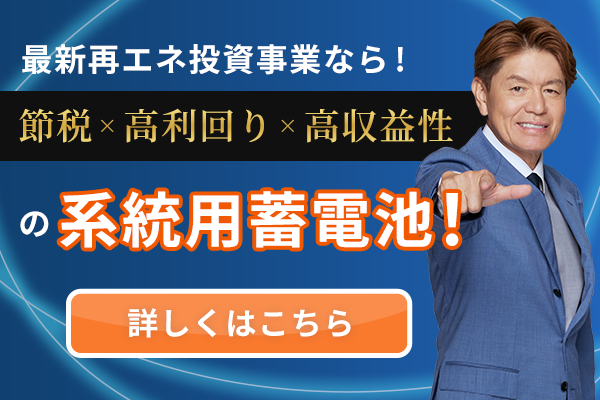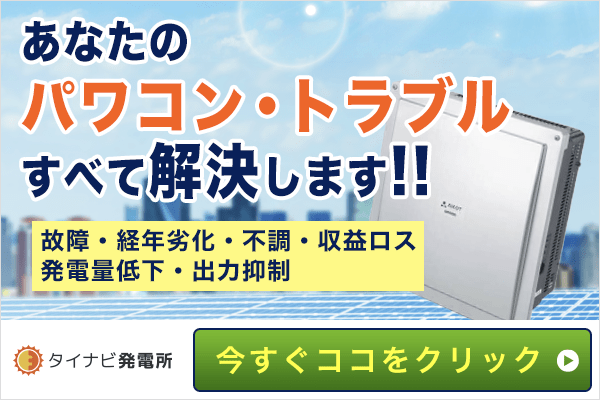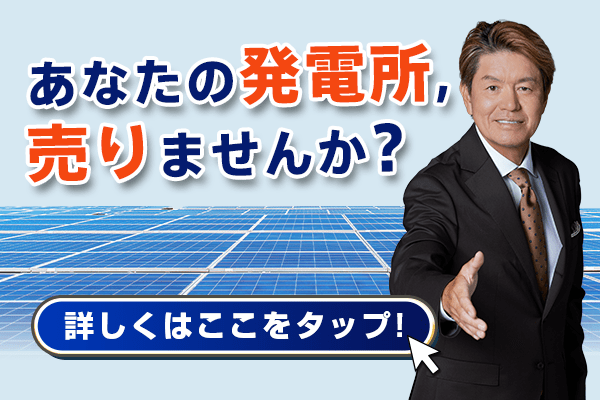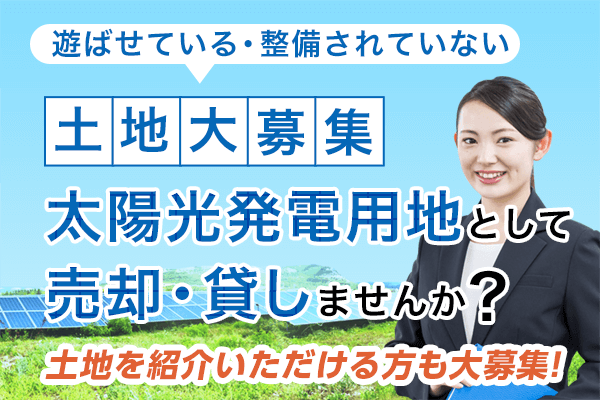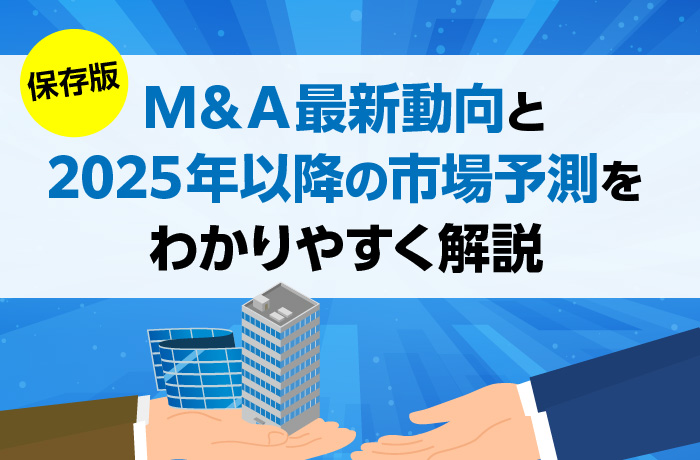
再生可能エネルギー業界は、国が目指す電源構成の比率として、2030年度に36%~38%を目指しており、2050年度の再エネ比率目標は50%~60%となっています。特に2030年度の目標達成には、太陽光・風力発電が2019年比よりも2倍以上に増加しないと実現が困難な状況となっています。
この数年はNONFIT発電所の急激な増加が目立つ一方で、太陽光発電所の増加に伴う出力制御(余った電気を捨てる)の問題がクローズアップされており、2025年現在は電気の需要・供給をコントロールする手段として、全国的に系統用蓄電池の開発や、FIT発電所に蓄電池を併設するFIP転換モデルが伸びています。
再生可能エネルギー業界は2012年のFIT(全量固定買取制度)により、太陽光バブルのような状況から約10年以上が過ぎましたが、近年の電気料金高騰や電気需要家の多くが再エネ100%の電気を希望するニーズが高まり、自家消費型太陽光が全国的に増加しています。そして、オンサイト型・オフサイト型など様々な設置方法から、いわゆる0円で太陽光発電などを設置できるPPAモデルもこの数年の主流となりました。
このように、再生可能エネルギーを使うニーズと供給する手法が年々増えており、それをコントロールする蓄電池が大きなカギとなっている状況です。
当然、このような変化の激しい市場では競争が激化しており、再エネ業界におけるM&Aも増加しています。2024年上半期(1~6月)には、電力・ガス業界全体でのM&A件数が49件に達し、前年同期比で26%増加しています。このような流れは、今後も年々高まっていくと予想されます。
では、再エネ関連企業の経営者にとっては、市場を理解するだけでなくどのような出口戦略を取るべきでしょうか?
どの事業が会社の価値を高めるのか?会社の価値を常に知る必要があります。
本記事は、再エネ業界で14年間にわたりタイナビシリーズ等のWebプラットフォームをを展開する株式会社グッドフェローズのM&A専門家が最新のM&A動向を解説し、具体的に会社売却・買収を考えている経営者の皆様へ、エネルギー業界に特化したM&A仲介サービス「タイナビM&A」についても解説しますので、最後までぜひお読みください。
再生可能エネルギー業界の過去・現状・今後の展望

再エネ業界関連企業の方にとっては、この14年はまさに浮き沈みの激しい業界でした。まずは、この14年間を簡単に解説します。
1:FIT時代(2012年~2019年)
再生可能エネルギーは2012年のFIT制度(全量固定買取制度)とグリーン投資減税等の税制優遇制度により、全国各地で発電所が爆発的に増えました。FITの売電価格は40円(税別)で20年間の固定価格買取からスタートしましたが、その売電価格は毎年下落し、低圧発電所においては2019年の14円(税別)を最後に終了しました。ただし、売電価格が下がっても調達・建設コストが減少したことで、同じような利回りで発電所の建設が続く状況が続きました。
風力発電では小型風力発電所が2015年頃にブームとなりましたが、日本の風況が複雑であるため、小型風力発電所の成長は見込めない状況となりました。
2: FIT終焉~卒FIT到来(2020年~2021年)
多くの太陽光関連企業は2019年頃から全量FIT頼みのビジネスモデルを展開していたため、FIT終了に伴い撤退・倒産が増えました。ただし、蓄電池に対する国の補助金がこの頃からスタートしたことや、住宅用太陽光発電の売電期間がちょうど終了したことにより、住宅用太陽光発電・蓄電池の業界に戻る企業が増加しました。
しかし、2020年~2022年頃は太陽光・蓄電池関連企業にとって非常に厳しい時代となりました。
3:新電力危機・自家消費・NONFITの到来(2022年~2023年)
ロシア・ウクライナ問題によるLNG価格の高騰により、電力卸売市場(JEPX)の価格が通常の10倍以上に高騰しました。この影響で、電力自由化を契機に多くの企業が電力業界に参入したものの、多くの電力会社が倒産・撤退を余儀なくされました。
しかし、この問題により電気料金が高騰したことで、個人・法人ともに自家消費への関心が高まりました。これにより、自家消費のために太陽光発電や蓄電池を導入する動きが加速しました。
また、FITに依存しない非FIT発電所(NONFIT)への購入ニーズも増加し、全国の太陽光関連業者による土地争奪戦がスタートしました。太陽光発電所はNONFIT発電所として堅調に件数が伸びている一方で、九州電力・四国電力・中国電力管内を中心に出力制御(電気の需要が少ない春・秋に太陽光などの電気が使われずに捨てられている問題)が社会問題化しています。
この出力制御の問題は、2025年時点でも依然として解決しておらず、太陽光発電所を売却する事業者が増えている状況です。
4:DR可能な蓄電池の到来(2024年~2025年)
近年は再エネ業界においては、DR※デマンドレスポンス(電力需給のバランスを調整するために、需要側(電力消費者)が電力需要をコントロールする為)において、蓄電池が最も成長・注目されており、住宅用・産業用・系統用を問わず、国からは蓄電池に対する手厚い補助金がでております。これにより、太陽光と蓄電池のセット提案が標準となりつつあります。
例えば、再エネ発電所に蓄電池を併設する動きが加速しています。太陽光発電所に蓄電池を設置するFIP転(フィード・イン・プレミアム)制度だけでなく、出力制御リスクの低減や、需給バランスの調整が可能な大型系統用蓄電池を設置する為に、全国各地のEPCが土地集めに集中しており、NONFIT以上に過熱している状況となっております。
このように、再エネ市場環境は毎年大きく変化しています。
再エネ業界のM&Aでおさえておくべきポイント
.png)
今後、再エネ業界で出口戦略を考えている経営者及び再エネ業界で買収を考えている企業は、次のポイントを押さえておく必要があるでしょう。
電気を安定価格で供給する方法としては、安定調達が欠かせませんが、その主流モデルとしては、PPAモデル・NONFITがありますが、蓄電池を活用したモデルがこれから成長するでしょう。
FITからFIPへの移行(太陽光発電所+蓄電池)
FIT終了に伴い、FIP制度への移行が進む中で、価格変動リスクが高まっています。蓄電池の活用により、安定的な収益及び供給が可能となります。
今後は高圧・低圧等などの多くの発電所に蓄電池が設置されて、FIP転が加速するでしょう。特に九州電力や北海道電力管内では、再エネの導入量が増加し、全国的に系統接続容量が限界に近づいています。
これにより、再エネ発電所の新規開発が制限され、既存案件の買収や蓄電池併設が戦略として重要になります。
系統用蓄電池の開発
系統用蓄電池は補助金等の影響で、まだ導入量は30件未満ですが、国内の電力需給安定に向けた大きな施策であり、国の出力制御問題や需給バランスの調整に欠かせない存在となっています。
今後急成長するビジネスであり、土地の確保から開発能力までを持つEPC等が買収対象となる可能性は高いでしょう。
リパワリング・O&M(運営・保守)事業の重要性
安定した収益を確保するためには、O&Mの効率化が不可欠です。日本全国の発電所を管理・リパワリングして、発電量の維持向上ができるEPC等が買収対象となる可能性は高いでしょう。
どの業界でもありますが、M&Aを通じてO&M事業を統合し、スケールメリットを活かす動きが増えると予測します。
今後再エネM&A市場に影響を与える制度について

今後予定されている制度変更で、市場に影響を与える内容について記載します。
制度内容の詳細によっては大きく変化する可能性があります。
売電価格大幅増加!初期投資支援スキームの導入
経産省の発表により、住宅用・産業用ともに現行の太陽光FIT価格が大幅に増加します。これは、初期コストを現状の10年程度から4年~5年程度で早期に回収させるための変更です。
住宅用:24円/kWh(~4年)、8.3円/kWh(5~10年)※現状は15円/kWh
産業用:19円/kWh(~5年)、8.3円/kWh(6~20年)※現状は11.5円/kWh
これにより、大幅な導入量が短期的に増えると考えられ、初期投資回収後の蓄電池設置が見込めます。この制度を活用してこの数年間販売件数を伸ばしたEPCは、4年~5年後に蓄電池設置の見込み客が増えることで、会社の価値向上が見込まれます。
長期安定適格太陽光発電事業者
国は日本全国の発電事業者を一部の事業者に集約したいと考えています。こちらの詳細に関しては正式な発表はありませんが、この認定を受けるにはかなりのハードルが高いとされています。
しかし、認定を受けた場合は以下のようなメリットがあります:
- 住民説明会が不要
- パネル増設時の積立金対応
- 売却情報の先行公開などの支援
この認定は、50メガワットの発電所を保有する実績などが必要なため、一時的に発電所のM&Aが加速する可能性があります。また、認定を受けた企業は今後大規模な発電所の買収合戦が予想されます。
近年の再エネ業界M&Aの概要
近年の再エネ業界でのM&A事例です。発電所を保有する企業の買収が多いですが、既存事業の拡大も目立ちます。以下は既にプレスリリース等で公表されている情報となります。
- □NTTとJERA、再エネのGPI買収を発表
- □東急不動産がリニューアブル・ジャパンを買収、再エネ事業1.6GW超
- □大東建託、バイオマス発電会社を買収
- □スマートエナジー社、アドラーソーラーワークス社をグループ会社化
- □高島が太陽光発電システム販売・施工会社を傘下に持つサンワHDを買収
- □株式会社サンヴィレッジが株式会社フロンティアエナジーの全株式取得
- □株式会社Looopと東急不動産株式会の資本提携
このようなM&A・資本提携事例より、今後どういったM&Aが注目されるだろうか?
2025年度以降に予想されるM&A動向
2025年以降、再エネ市場ではさらなるM&Aの加速が予想されていますが、そのM&Aパターンを大胆に予測します。
1. FIT発電所を大量保有する企業の買収
大規模発電所保有(FIT終了に伴い、FIP制度への移行)を目的とした大規模なFIT案件を大量に保有する企業への買収、特に新電力等の電力供給会社が発電所アセットを大量に保有する企業との資本提携や買収が予想されます。
2. 系統用蓄電池市場の統合M&A
系統用蓄電所事業規模の拡大を狙う企業が系統用蓄電池のEPC(設計・施工会社)への買収
3. 発電所O&M企業の買収
O&M(運営・保守)事業の競争力強化を目的として、発電所の管理を行う企業への買収
4. 地域特化型EPCの全国展開
全国展開するために、大手EPCが特定地域に強みを持つEPC(太陽光や蓄電池の設計・施工)への買収
5. 再エネ100%を目指す大手事業会社・電力による買収
再エネ100%を目指す企業(再エネ電源供給率を高めたい電力会社)による、NONFIT/FIP/FITを大量に保有している事業者の買収
では、実際に再エネ業界等で会社売却・事業継承・M&A戦略を検討中の企業はどうすれば良いのでしょうか?まずは、業界に特化したM&A会社を探すのはどうでしょうか?
業界に特化したM&A会社に依頼するメリット

今後M&A(買収)を検討している企業や、出口を模索する再エネ関連事業者はどこにM&Aを依頼すべきでしょうか?
M&A業界に多数の仲介サービスを提供している企業がありますが、数が多くてどこに頼めば良いか難しいでしょう。
そこでオススメなのが、業界が狭いほど業界に特化しているM&A会社をお勧めします。
<業界に特化したM&A企業に頼むメリット>
- ● 専門的な知識・経験
業界特有の規制、事業などに精通しているため、適切なアドバイスが可能。 - ● ネットワークの活用
業界内の買手・売手ネットワークを持っており、マッチング精度が高い。 - ● 案件価値の正確な評価
業界特有の収益モデルやリスクや市場性を考慮し、正確な企業価値を算出可能。 - ● 交渉力の強さ
業界内での豊富な実績により、買手・売手双方にとって有利な条件での交渉が可能。 - ● 契約・法務対応のサポート
業界特有の法的事項に精通し、スムーズな契約締結をサポート。
★ 業界特化のM&A会社に依頼することで、案件の成立スピードや条件が大幅に改善します。
再エネ業界でM&A(買収・売却)を検討中の方へ – タイナビM&Aの活用

再エネ業界に特化したM&Aを検討している方におすすめなのが、株式会社グッドフェローズが運営する「タイナビM&A」です。
グッドフェローズは、再エネ業界でタイナビシリーズ等のWebプラットフォームを展開しており、太陽光・蓄電池・PPA・新電力・NONFIT・蓄電所・風力・バイオマスなどの関連企業を事業を通じて全国規模のネットワークを構築、日本全国の太陽光発電事業者の約20%を会員データベース化しております。
- ● 豊富な業界ネットワーク:1,000社以上(メーカー、商社、大手EPC、電力会社)のエネルギー関連企業
- ● 経験豊富なチーム体制:10年以上の実績を持つプロフェッショナルが対応。
- ● 着手金・相談料無料:成功報酬型でリスクなし。
- ● 高いマッチング率:エネルギー事業に精通しており、企業価値を適切に算定。成約率は33%。
「タイナビM&A」は、再エネ案件に関する専門的な知識を持ったプロフェッショナルが対応し、事業ポートフォリオの最適化や収益の最大化を支援します。
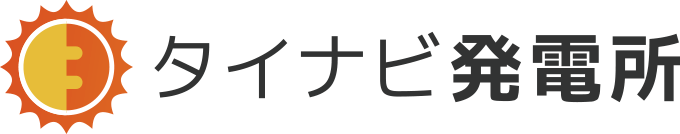
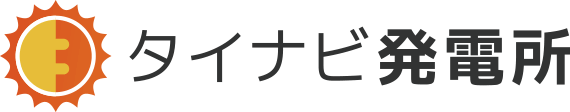




_m.png)






_s.png)

_s.png)